バスケットボール。
おそらく、これまでの人生で僕が一番夢中になった、もの。
同世代にはありがちでしょうが、バスケを始めたきっかけは、スラムダンク。
当時サッカー少年だった僕ですが、リョーちんかっけえ、なんて言いながら、一度バスケをやってみればたちまち虜になり、部活でも一人でも時間が許す限りボールを触っていました。
結局、小学校高学年から始めて今から数年前まで、20年以上バスケをやることになります。
長い間ひとつのことをやっていれば、それを通じてたくさんの出会いがあるもの。
ふと思い出したのは、その中でも印象深い出会い。
僕が高校を卒業して、アメリカに留学したときのこと。
学校裏のバスケットボールコートが僕の居場所
カリフォルニアの田舎。
僕が通った学校があったのは、娯楽施設がひとつもない、最寄りのスーパーまで歩いて20分くらいかかる町。
町の中に信号はひとつだけ。
広大な大地をまっすぐな道がどこまでも続くような、そんな場所。
学校に入ってすぐ、バスケットボールチームのコーチにチームに入りたいと話をしたものの、トライアウトが終わっているとから「NO」だと言われます。
僕がチームに入りたかったのは、単純にバスケが好きだった、という理由だけ。
バスケができる環境があれば、まあいいか、という気持ちでした。

学校周辺を歩いてみると、学校の裏にバスケットコートがあるのを見つけます。
寮に戻り、スーツケースに詰め込んでいた空気が抜かれて凹んだボールを取り出し、同じく持ち運んでいた小型の空気入れで空気をいれ、着替えてバッシュを履くと、早速コートに行き、ひとりでバスケを始めます。
その日から、屋根もないストリートコートが、授業以外の時間の、僕の居場所となりました。
毎日通っていると、同じようにバスケをしにくる若者に出くわします。
冷やかしでよく1on1を申し込まれました。
これでも一応真剣に部活に取り組んでいたほうなので、冷やかし程度では相手になりません。
一度真剣に対峙すれば仲良くなるのですが、レベルに差があり徐々に辟易としてきます。
それを避けて、授業前の早朝に、コートに行ってみることにしたのでした。
マーカスとの出会い
早朝。
当然ひとりだろうと機嫌よくコートに向かうと、ボールがはねる音が聞こえてきます。
うわー、先客。
ひとりでコートを自由に使えると思っていたのでがっかりしつつコートに近づいてみると、タンクトップの若者がひとり、シュートを打っていました。
黒人の男。
正直な話、この頃の僕は黒人が苦手でした。
寮内でもHIPHOPを常に爆音で流していて、ノリはやんちゃでとにかく面白いのですが、話していることがこの時の僕にはさっぱりわかりませんでした。それスラング??って。英語の聞き取りができない、僕が悪かったのではありますが。
また、一部ではあるのですがアジア人を小馬鹿にする面もあり、うまく付き合えていないのが実情でした。

そんなこともあり、僕はそろりとコートにはいり、彼とは逆側のゴールを陣取ります。
人がいるとはいえ他には誰もいないので、気持ちよく動けます。
と、僕以外の物音が聞こえないので帰ったのかなと反対側のゴールを見ると、彼が僕のほうに歩いてくるではないですか。
わわわ、やめて、ひとりにしておいてくださいまし。
気にしないふりをして、ひたすらシュートを打っていると、彼が僕の背中に声をかけてきました。
「いつもここでプレーしてるのか?」
振り向くと、彼が手を差し出してきます。
あれ、言っていることがなんとなくわかった。
それに、彼、他の黒人と雰囲気が違う。
握手をしながらそんな風に思いました。
肩から腕にかけての筋肉を見るだけでトレーニングをしている身体だということがわかります。
背はそこまで高くない、と当時は背が高い人ばかりで感覚が麻痺していましたが、いま写真を見ると190cm前半くらいだったでしょうか。
彼はマーカスと名乗りました。
話してみると、学校のバスケットボールチームのメンバーで、朝はそのコートで自主練習していたとのこと。
とまあ、わかったのはその程度でやはり半分も言っていることが理解できません。
会話が途絶えます。
若干の沈黙のあと、彼が1on1をしようと言ってきます。
バスケットボールチームのメンバーとプレーできるなんて文句ない。
まったく喋らずひたすらプレーする僕ら。
初の対戦は、僕の完勝でした。
言葉ではなくバスケットボールを通じて会話した
「明日もコートには行くか?」
1on1を終えて2人で寮に戻る道すがら、彼が聞いてきます。
僕がうなづくと、彼は次の日の朝に僕の部屋にくると言います。
「いや、大丈夫、自分でコートに行くよ」
そう伝えるも、喰い違う会話。
それから毎日、雨が降っていない限り、朝方に彼は僕の部屋にくるようになりました。
律儀に早朝に僕の部屋を訪れては、扉をノックするのです。
バスケットボールチームのメンバーの割には動きが鈍いな、と思っていたのですが、彼は腰を痛めていました。
そのため、毎朝の練習は彼のメニューを2人でこなしました。
軽いフットワークからシュート練習……と毎日ストイックにやっていた記憶があります。
そして〆には必ず1on1。

言葉はいつまで経っても半分くらいしかわからないのですが、その時間だけは気持ちをやり取りできている感覚がありました。
身体をぶつけ合い、会話をしているような、感覚。
あくまで感覚なのですが、彼もそう感じてくれていたように思います。
最初の頃は僕が勝つことが多かったのですが、2ヶ月も経って彼の身体の調子が戻ってきた頃には、僕が勝つ回数は激減することとなりました。
さくっと僕を抜いてダンク、なんてこと、しよる。
チームのほうでも彼の出場機会が増えてきて、僕も自分のことのように喜んでいたころ、彼から悲しい知らせを聞くこととなります。
彼と僕を繋いでいたのは間違いなくバスケットボールだった
その頃になると、マーカスは頻繁に僕の部屋を訪れるようになります。
お互いの家族のことを話したり、僕が彼に数学を教え彼が僕に英語を教えたりと、バスケ以外でも共に過ごす時間が増えていきました。
そんな折、いつものように彼が僕の部屋を訪ねてきます。
「入れよ」と促しましたが、いつもの陽気な雰囲気がありませんでした。
「大事な話がある」
彼が自分の部屋で話したいと言うので、僕は彼について彼の部屋に入りました。
向かい合って座ると、真剣な面持ちで彼が話を始めます。
学校を辞めて地元に戻り仕事をする。
父親が仕事を解雇されたため、家族、特に妹のために金を稼がないといけない、といった内容でした。
元々、貧乏なんだ、と。
学校を辞めたくない、ここから離れたくない、そういう彼の言葉は切実でした。
特に、バスケットボールを続けたい、という言葉が僕に深く突き刺さります。
彼は、スポーツ特待生でした。
ただバスケが好きでやっている僕とは重みが違うことに気付かされました。
好きなことを好きなようにやれている自体、自分は恵まれているな、と。
お互いが肩を落としている中、「見せたいものがあるんだ」と彼がベッドの下から箱を取り出しました。
透明のケースから、なんとも派手でごつい指輪が見えます。
彼はその指輪を手に取ると、僕の手のひらにのせてくれます。重たい。
指輪は上面が四角くなっており、そこに数字が刻まれています。
数字の下には彼の名前。
そして、数字と名前を囲うように「CHAMPIONS」という文字と年号が刻まれています。
彼は、高校時代のチャンピオンリングだと、言いました。
数字は彼の背番号、州で優勝したチームにいたのだ、と。
衝撃的でした。
州で優勝なんて、よっぽどのこと。
「お前にしかこのことは話していない。他のやつには黙っていてくれ」
当時僕らのいた学校は、バスケットボールが強いわけではなく、むしろ弱小でした。
なぜこんなところに、と思ったのですが、彼にもバスケットボールの有名校から声はかかっていたようです。
しかし、最近まで影響のあった故障をしてしまったことでそれも破綻となり、いまの学校に入学したというのです。
チームメイトには身の上は伝えずに、ひたすら故障を治すべく努力していたのでしょう。
彼は、バスケットボールが好きだ、バスケットボールを続けたい、と何度も言っていました。
きっと今のようにはできなくなる、と。
そして、「僕らを繋いでくれたバスケットボールを、これからも愛し、続けていって欲しい」と言うのでした。
その日の夜、彼は学校を去りました。
言葉がなくとも伝わるもの
次の日の朝、いつものように目を覚まし、バスケをする格好に着替えます。
そしてベッドに座り、ドアがノックされるのを待ちました。
当然のようにノックされることのないドアを見つめ、彼がいなくなったことを実感しようとしていたのだと思います。
結局、その日は、僕はコートには行きませんでした。
そのまた次の日。
彼の言葉を思い出しつつ、コートに向かいます。
それまでと同じ、早朝の時間。
誰もいない、コート。
コートに立ち、ドリブルを始めます。
自分のドリブルする音しか聞こえないのが、妙に寂しい。

その時見た、空。
鳥の声とただただ青い空が、なぜだか印象に残っています。
会話することも当然大事でしたが、僕の英語力がなかったため、思っていることをすべてやりとりすることはできていませんでした。
そんな状況がもどかしかったですし、彼も同様だったでしょう。
それにもかかわらず通じ合えた感覚があったのは、きっと、毎朝2人でバスケをすることで、僕らは言葉を交わさずとも会話をしていたのだと思います。
その日のお互いの気分・体調・想いなんかを、身体をぶつけ合うことでやりとりしていた感覚。
その後、彼とは数回手紙をやりとりしてそれっきりになっています。
彼はパソコンが使えなかったので、メールもできません。
それでも時々、彼のことを思い出すのです。
プロになったわけでも、有名校に入ったわけでもないので、僕はバスケットボールで成功したわけではないのですが、得たものはたくさんありました。
普通に話しているだけよりも、チームメイトとはバスケを通じてコミュニケーションがとれていたと思いますし、マーカスのように言葉はわからずともバスケを通じて仲良くなり、今でも交流が続いている友人もいます。
言葉がなくとも伝わるものって素晴らしいな、と、思うのでした。
バスケはもうやらなくなってしまいましたが、他の手段で言葉がなくとも伝わるものはないかと、模索しております。
できれば、身体をぶつけ合うような、そんな密度のもので。
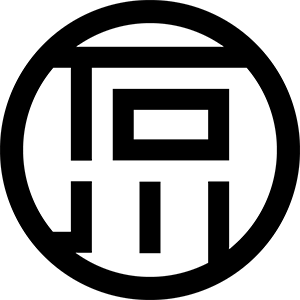

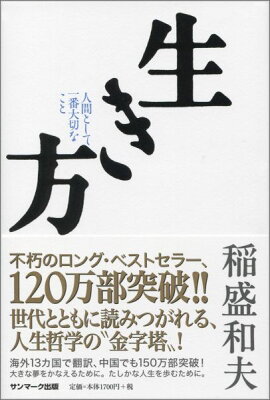


コメント
言葉じゃなくても伝わるのは愛情だけでなく、理由もなんですね。彼もきっと楽しかったと思います、けれど、人に寄っては好きや上手いだけじゃ食っていけないこともあるのは事実で…彼が今もまたたまにはダンクを決める姿を想像しつつ応援したいものですね。
紫苑 (id:buraxtudo) さん
ありがとうございます。彼がバスケをしていたのはある意味家族のためでもあり、彼がそれをやめた理由も家族のため。バスケをしていなくとも、いまは彼の家族が皆幸せにいてくれたらいいな、と祈っております。